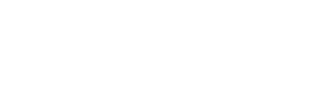紙が発明されたのは、今から2000年近く昔の中国でのことです。
最初は木の皮や使い古した布などを水につけ、それを棒で叩いて繊維を採り、紙にしていたといわれています。
この方法が、西暦610年(飛鳥時代初期)の頃に、高麗(今の朝鮮)からやってきた僧侶によって、初めて日本に伝えられました。
我が社創業のルーツである関氏は、長い戦国時代の終わった1600年代の初頭に、土佐藩24万石の新藩主となった山内一豊の一行に、近江商人の故郷・近江八幡の辺りから加わって土佐に移住してきました。
その土佐は、古い時代、飛鳥や奈良などの国の中央からは僻遠の、瀬戸内海によって隔てられた四国の、かつ、峻厳たる四国山脈の向こう側の太平洋に面した地でありました。
しかし土佐は、古くから紙の産地として知られ、長く、“和紙王国・土佐”と呼ばれてきたのです。
では、そもそも貴重な和紙の技術は、その遥かなる土佐にどのようにして伝わってきたのであろうか?
伝聞では、四国山脈の向こう側の伊予(愛媛県)から伝わってきたとされています。
江戸時代よりも遥か以前のことです。
それは、まさに“秘法”ですから、その伝授は、さぞや厳重なことであったに違いありません。
現に、伊予からつながる山間の地域に、今も尚、厳しい“秘法”秘匿の歴史を持つ場所が残っていると聞きます。
“土佐日記”という平安時代に書かれた有名な紀行文があります。
作者は、京都から土佐へ“国司”として派遣された貴族である紀貫之(生年872年頃~没年945年頃)です。
“国司”とは、“地方行政長官”のことです。
その紀貫之が土佐に赴任中、製紙業を奨励したことが伝えられています。
そもそも何故、土佐に製紙業を奨励したのでしょうか?
それは、紙が当時すでに、格別の貴重品であったからであり、その上に、土佐の山河が、抄紙に必要な清涼で豊かな水に恵まれ、気候の上でも、朝晩の寒暖の差が激しく、原料となるべき楮(こうぞ)、三椏(みつまた)の生育に適していたからです。
清涼な水の源は、西日本一の高峰・石鎚山(1982m)です。
その石鎚山に源を発し、高知県中央部の狭い平野を流れ下って太平洋に注ぎ込むのが清流・仁淀川(全長124km)です。
仁淀川は、全国の一級河川の中で水質第4位、生活圏を流れる川としては、水質第1位の清流です。
その仁淀川下流に広がる四国山脈南端の小さな平野の土佐市やその周辺一帯が、“和紙王国・土佐”の中心地域なのです。
それらのことは、高知県吾川郡伊野町の「紙の博物館」歴史コーナーに紹介されていますが、それにしても、土佐は、如何に長く、都から僻遠の地であったことでしょうか?
紀貫之が任期を終え、京の都へ帰国したときのルートは、土佐湾から内海の奥へ入り込んだ大津と呼ばれていた政庁から、外海に出、途中の港々を辿って、ときには日和待ちをしながら、一ヶ月以上もかけて、荒波の室戸岬沖を回り込んで、徳島の鳴門から淡路島の南岸を上り、ようやく淀川の河口に出、京の都に戻ったのです。
その大難儀であった道中の記録が、有名な「土佐日記」として遺されているのです。
険峻な四国山脈は、越えることを許さず、中央との往還は、室戸岬を回り込む海のルートか、あるいは、四国山脈がようやく西の端に尽きる辺りの峠を越える、遥かな迂回ルートしか無かったといいます。
しかし土佐の人たちは、そのように遥か僻遠の地であったからこそ、“土佐和紙”独自の技術を、長い間にわたって発展させ、“土佐特産”として全国に知られるものとしたのです。
そして、その土佐へ入府する新藩主に従ってやってきた、創業者の祖先の関氏は、仁淀川下流に広がる平野の一角の集落に定着し、累代、土佐和紙抄造に携わってきました。
それ故に、我が社は、創業時より自然に敬意を払い、近江商人の“三方良し”を踏まえて、“笑顔を通じて共存共栄”を経営理念として掲げているのです。
(2020年3月)